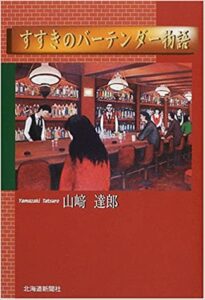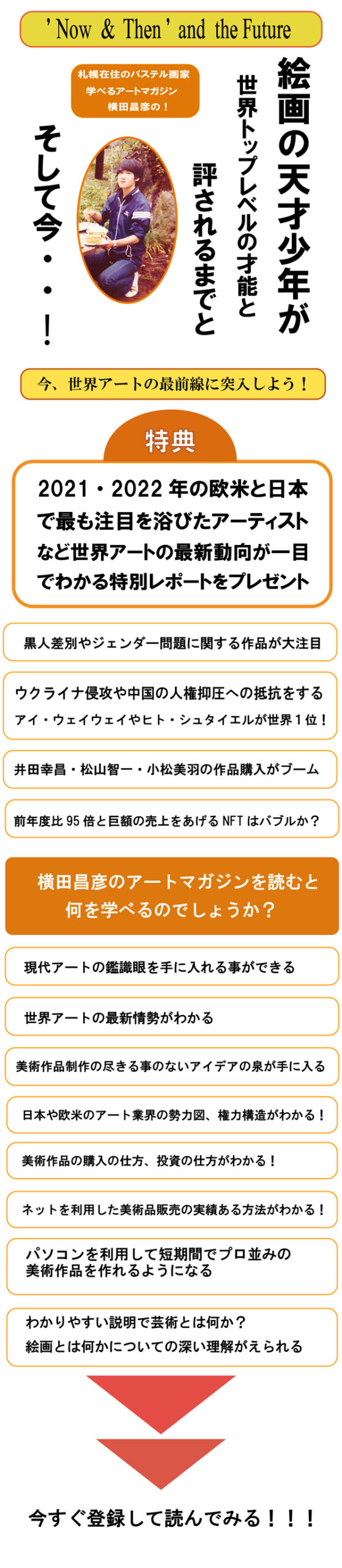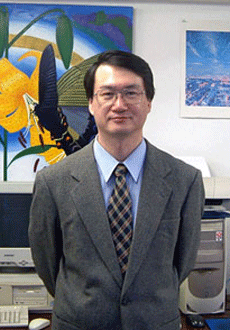調性とは色の事である
今回は再び「音楽を絵画に翻訳する場合、調性(ハ長調、イ短調など)はどのような法則になるのか?」ということについて、歴史上初めて私がその法則を発見し活用し始めたことを解説いたします。
前回の記事はこちらです。
音階は絵画ではどのように表現すれば良いのか?
音楽を絵画に正確に翻訳するには、まず音階すなわち音の高低をどのように絵画化すれば良いかという課題にぶち当たります。
音楽では音階が上がるにしたがって音の周波数が上がります。

カンディンスキーが「トランペットの甲高い音は金属的な音で黄金色を連想させる」というように、それぞれの楽器にはある特定の色を連想させる感じがします。
そうであれば、トランペットの音階はこの図のようになるでしょう。

しかし、これでは説明できない事が起こってきます。
それぞれの濃淡のレベルがドレミファソラシドの音程にあたるなら、ハ長調とイ短調という調性音楽のどの調性も、画面上ではある色の視点となる濃度のみの違いとなってしまいます。
もっと分かりやすく説明すると、トランペットは黄色、パイプオルガンは緑色とするならハ長調の唄は黄色の濃淡、パイプオルガンのハ長調は緑色の濃淡となってしまいます。
曲はどの楽器で演奏しても、基本的な印象・心象は同じですが、曲をこのやり方で絵画に翻訳した場合、画面はある色のみの濃淡となり、どうやっても同じ印象にはならないでしょう。
今度は音階を光のスペクトラムに対応させてみましょう。周波数に合わせて対応させるとこの図のようになります。

このようにするとドの色は赤、レの色は朱色となります。
これだと主調の違いは説明が付きます。
ハ長調はドの色なので主調が赤の色。これより半音階ずれたのが短調なのでハ短調は朱色がかった赤が主調となる。
これならトランペットのソロの曲は、ミの音である黄色が主調のホ長調、またはホ短調の曲となる。主調色は色の違いとなり、なるほど音楽の長調は明るく、短調は暗く、さらにそれぞれの調性がもたらす情緒の違いも上手く説明できます。
つまり、長調は明るい感じの曲となりますが、それは赤とか黄色とかに対応する純粋な音だらからで、暗い感じの曲である短調は赤と朱色などの中間色ですこし濁った感じの鈍い音なので暗い感じがすると理解できますね。
昭和時代に国民画家と言われた梅原龍三郎の代表作に桜島の青と赤があります。
これは赤がハ長調、青がイ短調と言えますね。
まさに主調をともにするの主調ですよね。